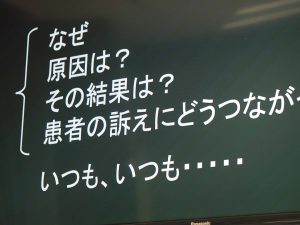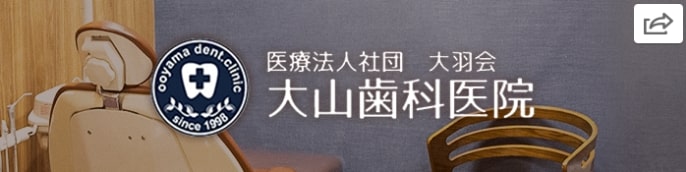医療としての矯正治療を通じて、全身との調和を考えた“最適な下顎位”を模索する歯科医療は、従来の「歯並びを整える」矯正治療とは一線を画す、より包括的で機能的な医療アプローチです。これは、口腔を“全身の一部”としてとらえる視点から、患者の健康とQOL(生活の質)を総合的に支えることを目的としています。
【1】なぜ“下顎位”が全身に影響するのか?
● 顎の位置と筋・骨格バランス
下顎の位置は、頭蓋骨・頸椎・背骨と連動しています。
不適切な下顎位は、以下のような全身への不調の引き金となることがあります:
- 頭痛、肩こり、首のこり
- 顎関節症(顎の痛み、開口障害、雑音)
- 姿勢の崩れ、頸椎や骨盤の歪み
- 呼吸機能の低下(気道狭窄)
● 咀嚼と脳・内臓への影響
正しい咀嚼は脳の血流や消化機能を活性化させますが、噛み合わせが悪いと…
- 咀嚼筋の過緊張
- 消化不良
- 自律神経の乱れ など、身体の内的バランスを乱すことも。
【2】医療としての矯正治療とは?
一般的な矯正治療との違い
| 内容 | 一般的な矯正 | 医療としての矯正 |
|---|---|---|
| 目的 | 歯列の整美・審美性 | 機能回復・全身調和 |
| 対象 | 歯・顎の位置 | 咀嚼機能・姿勢・気道・筋機能 |
| ゴール | キレイな歯並び | 正常な顎位と口腔機能の獲得 |
| 検査 | 歯科用レントゲン | 顎関節・気道・筋バランス・体姿勢まで評価 |
【3】“下顎位”を模索する診療プロセス
① 精密検査
- セファロ分析(頭部X線規格写真)
- 顎関節CT・MRI
- 姿勢・体幹バランス測定
- 筋電図、咬合力、呼吸検査など
② 顎の安定位の評価(中心位 or 機能位)
- 咀嚼筋の緊張を除き、顎関節が安定する位置を探索
- スプリント療法による一時的顎位誘導
- 日常生活での適応状況を経過観察
③ 治療計画の立案
- 咬合再構成を前提とした矯正装置設計
- 骨格の成長誘導(子どもの場合)や顎位の再設定
- 必要に応じて外科矯正や補綴治療を併用
【4】医療矯正によって得られる効果
- 口腔機能の正常化:咬合、発音、嚥下、呼吸がスムーズに
- 顎関節の安定:顎関節症の改善・予防
- 姿勢と筋肉のバランス改善:肩こりや首の痛みが軽減
- 気道の確保:睡眠時無呼吸症候群の予防や改善
- 心理的改善:食事・会話・見た目に対する自信の回復
【5】未来の歯科医療:医科歯科連携へ
こうした下顎位に着目した矯正治療は、今後ますます「医科歯科連携」が必要になる領域です。
整形外科、耳鼻科、呼吸器科、発達支援、小児科などと協力しながら、
「歯科は口だけでなく、全身を支える基盤」としての役割を果たすことが期待されます。
【まとめ】
- 下顎位は、全身のバランス・姿勢・健康に影響を与える大切な“軸”です。
- 医療としての矯正治療では、審美ではなく機能と全身の調和を第一に考えます。
- 顎の正しい位置を導き出し、筋肉・関節・姿勢・気道などの機能改善を目指すアプローチです。